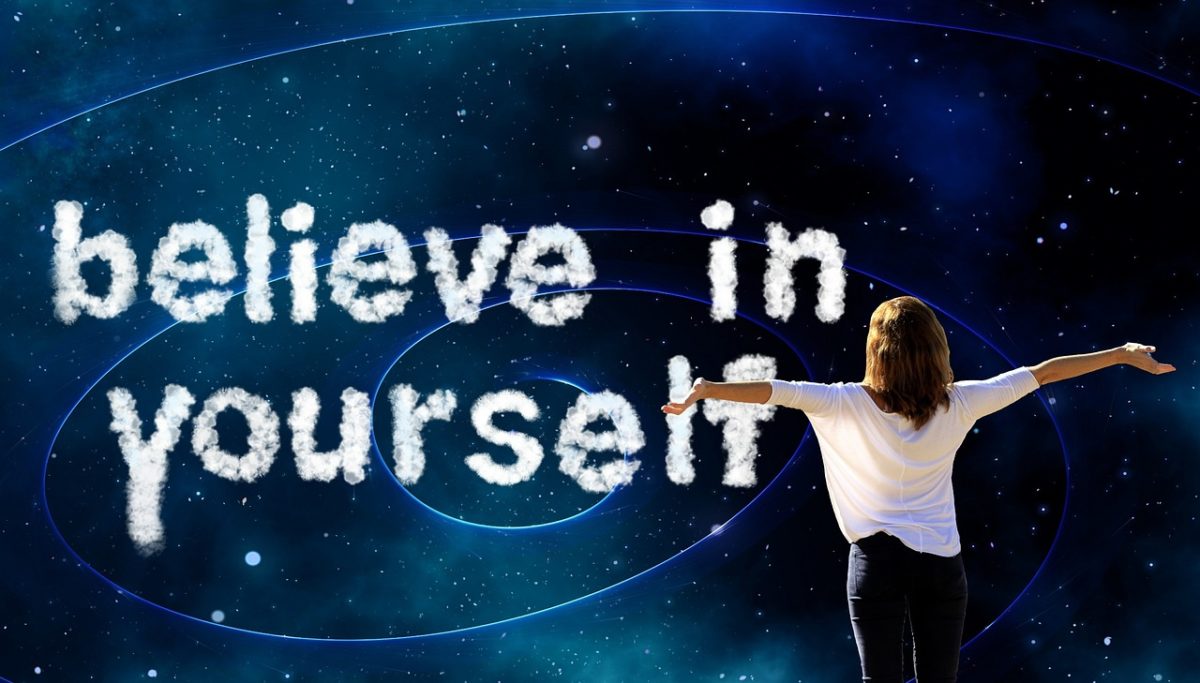金の斧か、銀の斧か
湖に斧を落としてしまった木こりの前に、神様が現れます。
そしてこう尋ねます。
「この金の斧か? それとも銀の斧か?」
きこりは、答えます。「いいえ違います。鉄の斧です」。
この話を、多くの人は
「正直に生きていくことが大切」という物語として覚えています。
けれど、本当に大切なのは、
彼が何を手に入れたかではありません。
大切なのは、
結果が分からないその瞬間に、
彼が何を基準に選んだかです。
彼は、
得をするかどうかも、
評価されるかどうかも、
分かっていませんでした。
それでも彼は、
目先の状況に惑わされず、自分が本当に持っていた斧を選んだ。
結果は、その後についてきただけです。
リーダーとは、役職のことではない
今回のテーマの人生のリーダーなるという、「リーダー」とは、
誰かの上に立つ人のことではありません。
自分の人生に夢を持ち、
主体的に責任を引き受けながら、
その夢に向かって進む人。
それが、ここで言うリーダーです。
だから私は、
すべての人に、リーダーを目指してほしいと思っています。
しかし、このリーダーへの道を阻むのが、
目先の結果に囚われるということです。
多くの人は、結果で判断を決めてしまう
私たちは日常で、こんなふうに考えがちです。
・うまくいったから、正しかった
・失敗したから、間違っていた
結果によって、
自分の判断そのものを裁いてしまう。
そして、その後の行動に制限をかけてしまう。
でも、ここには大きな落とし穴があります。
結果は、いつも自分の思い通りになるとは限らないからです。
結果だけを基準にすると、人は挑戦できなくなる
結果がすべてになると、人はこう考え始めます。
・失敗しそうだから、やめておこう
・評価が下がりそうだから、黙っていよう
・確実な道だけを選ぼう
・自分に責任が無いようにしよう
こうして、
挑戦しないことが“正解”のように見えてくる。
でもそれは、
自分の人生のハンドルを、
少しずつ手放している状態かもしれません。
本当に大切なのは「どんな判断から始まったか」
人生のリーダーになる人が大切にするのは、
結果そのものではありません。
どんな判断から始まったか。
・自分が大切にしている価値観に沿っているか
・都合の悪い事実から目をそらしていないか
・誰かのせいにする前提になっていないか
・他人の判断に従っていないか
この判断が整っていれば、
たとえ結果が思い通りでなくても、
その選択は間違いではありません。
正しい判断から生じた結果は「次に進むための情報」
正しい判断から行動した場合、
結果の意味は大きく変わります。
成功すれば、
「この判断は機能した」という情報。
失敗すれば、
「次はどこを修正すればいいか」という情報。
つまり結果は、
他人を責める材料でも、自分を責める材料でもない、
次の判断の質を高めるための材料になります。
金の斧を選んだか、銀の斧を選んだか。
それを知る前に、
彼はすでに「選ぶ基準」を決めていた。
ここに、リーダーとして生きるヒントがあります。
悪しき判断は、人生の主導権を曖昧にする
一方で、
・楽をしたい
・嫌われたくない
・責任を取りたくない
・目先の利益さえよければ良い
こうした気持ちが判断の中心に来ると、
人生の主導権は、少しずつ自分から離れていきます。
うまくいけば自分を正当化し、
うまくいかなければ環境や他人のせいにする。
ここでは結果は、
学びではなく、言い訳の材料になってしまいます。
主体的に生きるとは、完璧であることではない
人生のリーダーとは、
強い人でも、失敗しない人でもありません。
自分の判断を引き受け、
結果を受け取り、
修正しながら進み続ける人です。
迷ってもいい。
遠回りでもいい。
大切なのは、
誰かの人生を生きないことです。
リーダーを目指すあなたへ
これから何かを選ぶとき、
ぜひ一度、こう問いかけてみてください。
「この判断は、
うまくいかなくても、
他人や環境の責任にせず引き受けられるだろうか?」
この問いにYESと言える判断は、
あなたを確実に前に進めます。